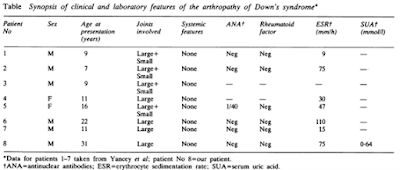緑膿菌が血培から生えたVAPで、
CLSI-M100 28th
Kucers' The Use of Antibiotics 7th edition
- Enterobacter (Enterobacter cloacae complex, Enterobacter aerogenes)
- Serratia marcescens
- Citrobacter freundii
- Providencia stuartii
- Morganella morganii
1. 誘導性/不安定型β-ラクタム
2. 誘導性/安定型β-ラクタム
例:カルバペネム3. 弱い誘導性/不安定型β-ラクタム
AmpC誘導能は弱いため、
したがって、
ピペラシリン・タゾバクタムを例にすれば、
AmpCはピペラシリンを加水分解し、
4. 弱い誘導性/安定型β-ラクタム
誘導能は弱く、かつAmpCが過剰に誘導された場合も、
- Design: 多施設RCT、Open-label
- P: Enterobacter spp、Klebsiella aerogenes、Serratia marcescens、Providencia spp、Morganella morganii、Citrobacter freundiiの血流感染。かつ、第3世代セファロスポリン、
ピペラシリン・タゾバクタム、メロペネムに感受性あり - I: ピペラシリン・タゾバクタム4.5g q6h
- C: メロペネム1g q8h
- O: 30日死亡率、臨床的失敗(5日目での体温or白血球増加)、
微生物学的失敗(3~5日目での指標菌検出)、 30日時点での微生物学的再発、の複合エンドポイント
結果:
- ピペラシリン・タゾバクタム群40名、
メロペネム群39名が割り付けられた - 主要評価項目達成は、ピペラシリン・
タゾバクタム群では38例中11例(29%)、 メロペネム群は34例中7例(21%)、リスク差8%(95% CI -12%~28%) - 微生物学的失敗は、ピペラシリン・
タゾバクタム群では38例中5例(13%)、 メロペネム群では34例中0例(0%)だった。リスク差13%( 95%CI、2%~24%) - 微生物学的再発は、ピペラシリン・タゾバクタム群0%、
メロペネム群9%だった - 微量液体希釈法による感受性率は、ピペラシリン・
タゾバクタムが96.5%、メロペネムが100%であった
結論:
- AmpC産生菌による血流感染症に対するピペラシリン・
タゾバクタムは、微生物学的再発は少なかったが, 微生物学的失敗が多くなった
- 染色体性AmpCの腸内細菌目(ESCPM)に対しては、
セフェピムかカルバペネムが鉄板 - ピペラシリン、セフトリアキソンも感受性があれば、
現場の判断で慎重に使っても良さそう - 血流感染はやめておいた方がいいかも(MERINO-2)